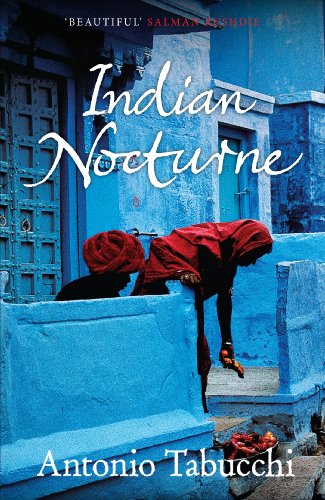今回のウクライナ侵攻では二次的な問題かもしれないが、トルコってフシギな国だな、と思ったひとも多いのではないか。実効性のほどはさておき、トルコがロシアとウクライナの仲介役となり、戦争当事国の外相会談がトルコでひらかれた。うん? なぜトルコなのか。
聞けばトルコはNATO加盟国でありながら、ロシアとの軍事協力を深め、ロシア製の地対空ミサイルも導入している。一方、ウクライナの最前線では、トルコ製の軍用ドローンがロシア軍に打撃を与えているそうだ。なんじゃこりゃ?
そんな二股外交のゆえんは、地図を見れば直感的にわかる。黒海をはさんで、トルコの対岸の左右両サイドにロシアとウクライナが位置しているからだ。わるくいえば分断と分裂、よくいえばバランスが、国家としてのアイデンティティや国民性と大きくかかわっているのでは、と地図を眺めているうちに思えてくる。
というのは牽強付会かもしれないけれど、表題作以前に読んだ Orhan Pamuk の作品では、もっぱらイスタンブールが舞台となっていた。イスタンブールこそはアジアとヨーロッパが衝突ないし融合する街、分断とバランスが渾然一体となった街だろう。これにローマ帝国以来、今日までの統一と分裂の歴史を重ねあわせると、なるほど、トルコってフシギな国だな、フシギが当たり前の国なんだな、という気がする。
さて "Snow" の舞台はイスタンブールではなく、トルコ北東部の街カルス(Kars)。地図で見ると、ほんとにトルコの北の先っぽのほうで、なぜ Pamuk はこんな遠隔の地を舞台に選んだのか。
この疑問は、なぜイスタンブールやその他の大都市ではなかったのか、と考えれば氷解すると思う。つまり、本書における軍事クーデターがもし中心都市で発生したとすれば、それは1960年と1980年に実際に起きた軍事クーデターの再現であり、スケールのはるかに大きな、おそらく政治一色に近い小説として描かざるをえないはずだ。それよりむしろ、「オルハン・パムクはここでおそらく現代トルコの政治状況の縮図を象徴的に、時には戯画的に描」きたかったのではないか。縮図なら、クーデターは「すこぶる限定的」であるべきで、それには「深い雪に閉ざされた」遠隔の地のほうがふさわしいだろう。
ここでは「文明の衝突、その一方で統一への希求といったさまざまなベクトルが見えてくる」。そこにファースやメタフィクション、ラヴロマンスなどをからませるとは、Orhan Pamuk って、ほんとにフトコロの深い、芸達者な作家だなと思わずにはいられなかった。
ぼくが初めて Orhan Pamuk のことを耳にしたのは、2006年、彼がノーベル文学賞を受賞したときだ。さっそく代表作とやらを何冊か買い求めたものの、すべて積ん読。
同年夏の甲子園決勝は、あのハンカチ王子とマーくんの投げ合いだった。その数日後、ぼくは勤務先の大先輩のお宅を訪問。(あ、この話はいつかも書いたっけ)。早期退職して数年になる先輩がそのとき、辞めてから「Orhan Pamuk も読みました」と、にっこり笑って話してくれたのを、いまでもありありとおぼえている。
それから干支が一巡した2018年、定年退職したぼくはようやく Pamuk の本を手に取った。以来、今回の "Snow"(2002)は6冊目(本書につづいて読んだ "The Red-Haired Woman" で7冊目)。これでたぶん、先輩が読んだものと思われる作品はほぼカバーしたはずだ。「ぼくも読みました」と、先輩がまだ存命のうちに報告したかった。
以下、先輩の墓前に捧げるべく、2006年以降のものもふくめ刊行順に既読作品を挙げておこう。
1. The White Castle(1985 ☆☆☆☆)
2. The Black Book(1990 ☆☆☆☆★)
3. My Name Is Red(1998 ☆☆☆☆★)
4. Snow(2002 ☆☆☆☆)
5. The Museum of Innocence(2008 ☆☆☆☆)
6. A Strangeness in My Mind(2014 ☆☆☆★★)
7. The Red-Haired Woman(2016 ☆☆☆★★★)
(下は、この記事を書きながら聴いていたCD。ジャズはつくづく「平和の音楽」だと思う)