なんでやねん! "The Colony" がブッカー賞ショートリスト落選とは!
下馬評ではロングリストの発表前から1番人気だっただけに、ぼく同様、この結果にびっくりした現地ファンも多かったようだ。いったい、なにが起きたのだろうか。
とそう疑いたくなるのは、ほかの入選作を見わたしても、未読の3作はべつとして、あとの3作はどれも "The Colony"(☆☆☆☆)を上まわる出来ばえとは思えないからだ。"Small Things Like These"(☆☆☆★★★)の入選は順当としても、"Treacle Walker" と "The Trees" はどうなのか。ぼく自身、妙な予感がして読んだので文句はいえないけれど、結果的に両書とも☆☆☆★。泡沫候補のような気がした。
こうなっては、未読のものが "The Colony" よりすぐれた作品であることを期待するしかないが、その可能性は低いかもしれない。なんだか今年の賞レースそのものに興味が薄れてしまった。
閑話休題。レビューにも書いたが、表題の一家の主人 Ben-Zion Netanyahu が実在の著名な歴史学者であることは、恥ずかしながら、巻末の Credits & Extra Credit を読むまで知らなかった。調べると、Ben-Zion はイスラエルの元首相ベンヤミン・ネタニヤフの実父。え、本書に出てくるエロ息子 Benjamin があのベンヤミンだったのか。
とそんな予備知識はなくても、これは大いに楽しめる「まことに味わい豊かなケッサクである」。レビューに盛りこめなかったエピソードをひとつだけ紹介すると、本書の語り手 Ruben Blum の娘が鼻を骨折する一件がとてもおもしろい。Blum もユダヤ系で、娘はあのユダヤ人独特のかぎ鼻の持ち主。彼女はそれをなんとかヘコませようと努力するのだが…
このホームコメディ以上に笑えるのが、Blum の家に Ben-Zion が妻子ともども、文字どおり土足で踏みこんできたときの「ドタバタ奮戦記」。「ブルム夫妻はネタニヤフ一家の常軌を逸した傍若無人ぶりにきりきり舞い」。宇宙的なまでにクレージーなコメディで、これが本書の読みどころのひとつであることはまちがいない。
一方、ここには現在のアメリカが、もしかしたら世界全体がかかえる問題の指摘もあり、ぼくはガラにもなく考えこんでしまった。Ben-Zion はこう力説する。What was true of Europe at the emergence of Zionism will one day be true for America, too, once assimilation is revealed as a fraud, or once it's revealed that the county contains nothing to assimilate to―no core, no connate heart―not just for the Jews, but for everyone. .... This is what I think of America―nothing. Your democracy, your inclusivity, your exceptionalism―nothing. Your chances for survival―none at all.(p.215)
1960年に Ben-Zion がおこなった講演の一節という設定だが、ぼくにはこれが21世紀の現代を生きる人びとへのメッセージのような気がしてならない。「ここで注目すべきはむしろ、そもそも現代のアメリカに多民族が同化すべきコアがあるのかどうか、という根本的な問いが発せられている点だろう。国民が核心的価値観を共有しない国家はいずれ崩壊する。ところが、『民主主義は空虚だ』とブルムはいう。1年前の作品だが、この彼の宣言は現在、アメリカのみならず国際社会全体に鳴らされた警鐘と解することもできよう」。
わが国も、いちおう民主主義国家ということになっていて、ウクライナへの支援を可能な範囲でおこなっている。ところが元大阪府知事は、「不幸にして戦争が始まった場合には戦争指導者や戦闘員の崇高な思想だけでなく一般市民の意思や犠牲も考慮した戦争指導が必要。一般市民は自分の命を捨ててまで何を守ると考えるか。自由、民主主義では抽象的過ぎる」とツイート。どうやらこのひとにとって、自由と民主主義は守るべき「核心的価値」ではないようだと察せられるが、彼の考えかたに賛同するかのように、ある調査では、外国からの日本侵略にたいして、「戦うという日本の若者は2割、様子を見るが4割、あとの4割は外国へ行き、状況が落ち着いたら帰国」とのこと。つまりこの国には、民主主義にかぎらず、守るべきものはほとんどなにもない、ということなのかもしれない、とぼくは思ってしまった。
が、そもそもぼく自身はどうなのか。You are nothing. といわれて反論できるだけの「核心的価値観」を、はたして有しているのだろうか。
とそんなことも想起させる本書は、「深刻な要素をはらみつつアハハと笑わせる。奇想天外なケッサクである」。造本がしっかりしていないせいか、読みおわるころにはペイパーバック版の本はバラバラ。内容をみごとに物語っているようで、おかしかった。
(下は、この記事を書きながら聴いていたCD。中島みゆきのアルバムはほとんどぜんぶ所蔵。久しぶりに、何巡目かを鑑賞中)



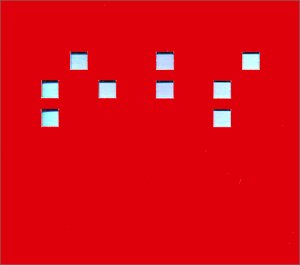


![おしゃれ泥棒 [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray] おしゃれ泥棒 [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41b5JEGkE8L._SL500_.jpg)