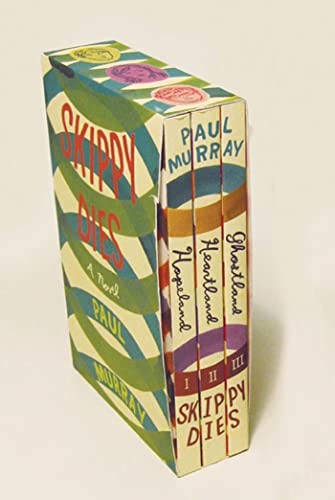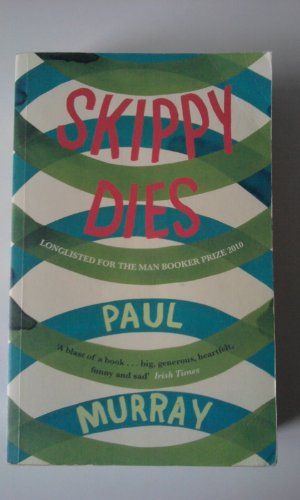今年のブッカー賞候補作、Paul Murray の "Skippy Dies" をやっと読みおえた。さっそく、いつものようにレビューを書いておこう。
[☆☆☆☆] 学園ものといえば青春小説と相場が決まっていて、たしかに本書でも青春の嵐が吹き荒れている。が、これは教師と生徒それぞれの立場から学校生活と私生活を描き、人生経験の場、教育現場としての「いまそこにある」学校を主な舞台とすることで、学校がいわば現代社会の縮図、いや小宇宙とさえ化した「総合学園小説」とでも呼ぶべきものだ。孤立、挫折、自己喪失、絶望、過去のトラウマ、良心の呵責、一時の激情、政治的野心、偽善と自己欺瞞。ここにはありとあらゆる負の感情が渦まき、それがときに猛烈な高ぶりを見せ、生徒も教師もおおいにゆれ動く。その嵐は同時に、純真無垢な心がひどく傷つきながらも、かすかな希望をいだき、充実した人生を求めてやまぬ証左でもある。冒頭、ドーナッツ屋で少年が突然死亡。その死にいたるまでの経緯がしだいに明らかにされ、さまざまな余波が広がっていく。ユーモラスな授業風景や、少年が在籍していたダブリンの名門男子校と女子校との合同ダンスパーティに代表されるドタバタ狂騒劇、あるいは青年教師が演じるラブコメディなど、当初は軽快なノリだが、しだいに上の負の感情がヒートアップ。やがて意識の流れの技法まで駆使され、現実と幻想の交錯するマジックリアリズムの世界が現出。ドラッグや不良グループ、パッヘルベルのカノン、地球外知的生命体や死者との交信、第一次大戦の秘話などと題材も多岐にわたり、そこへ定番の恋愛や友情のもつれ、親子の断絶などがからむ。総じて混迷する現代の象徴ともいえるような悲喜劇である。