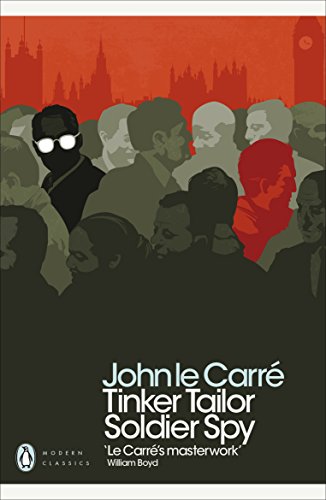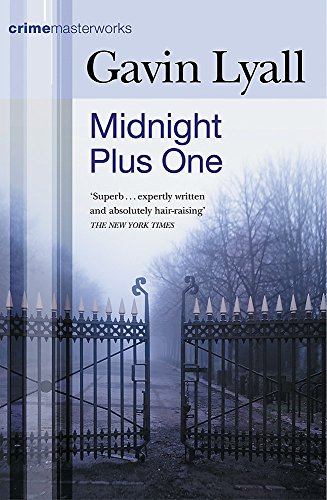ゆうべ、2013年のギラー賞一次候補作、Joseph Boyden の "The Orenda" を読了。Shadow Giller Prize という現地カナダのファン投票では1位を獲得した作品である。さっそくレビューを書いておこう。
[☆☆☆★★★] 途中から(史実を知らなくても)予想はつくものの、終幕の戦闘シーンが圧巻。読んでいて息苦しくなる。カナダの先住民ヒューロン族が立てこもるイエズス会の伝道所に、イロコイ族の戦士たちが大挙して襲いかかってきたのだ。1649年に実際に起こった事件だが、この山場もふくめて本書はじつにオーソドックスな歴史小説。アメリカ西部劇のカナダ版である。ヒューロン族の戦士とイロコイ族の娘、フランス人宣教師の三人が交代で話者となり、残虐な部族抗争と日々の農村生活、「悪魔に支配された」先住民への布教活動がことこまかに綴られていく。戦士同士の友情や、捕虜となったイロコイ族の娘がしだいに新しい家族の一員として溶けこむところなど、定石どおりだが読ませる。宣教師が先住民のアニミズムを否定し、白人が疫病を蔓延させたことも認めず、神による魂の救済を説く一方、先住民のほうは土俗的な風習を墨守。異文化の衝突というカナダ建国の歴史がありのままに伝わってくる。上の大事件も、思わず目をそむけたくなるような拷問も、いわば「産みの苦しみ」のひとつであり、過去と未来はつねに存在し、両者をつなぐ重要な役割を果たすものが現在であるとのメッセージには、カナダだけでなく、あらゆる国の国民文学としてじゅうぶん説得力がある。