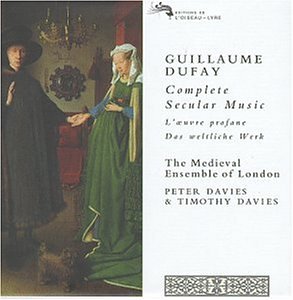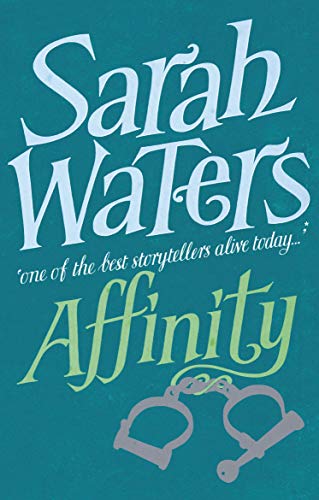ついにコロナか、それともふつうの風邪か、とにかく発熱。おまけに喉がやけに痛く、調べるとオミクロン株の症状にそっくり。実際何度あるのかはコワくて測っていない。きょうは何日かぶりに起きていられる状態なので(たぶん発症4日目)、この記事を書いている。
寝床のなかでは Orhan Pamuk の "Snow"(2002)を読んでいる。べつに無理をしなくてもいいのだけど、寝込む前のくだりがとても面白く、つづきが気になる。読んでいてしばらくすると目がまわりはじめ、これがこの世で最後の本か、などと考えたりしているうちに眠くなる。
同書が面白いのは、豪雪のさなか、トルコの田舎町を訪れた主人公の詩人がなにやらとんでもない事件に巻き込まれそうだ、という予感がするからだ。娯楽ミステリの序盤とおなじノリで、そういえば Pamuk の作品はどれも多かれ少なかれミステリ味がある。
ところが、邦訳が推理文庫に収められ、れっきとしたミステリであるはずの表題作のほうは、読みはじめたときからピンとこなかった。まず、ミステリというからには蠱惑的な謎の事件が起こるはずなのに、その事件に降霊術がからんでいると知り、白けてしまった。
もちろん、降霊術うんぬんは目くらましで、じつは、という設定になっている。しかしそれが降霊術というだけで目くらまし効果が薄れてしまい、どうせなにか裏があるんだろうと思ってしまう。このとき、降霊術はすべてトリックというのは現代の常識であり、本書は19世紀ヴィクトリア朝時代の話なのだから、現代の尺度で測ってはいけない、という理屈も成り立つわけだが、それはタテマエ。なんだ、降霊術か、というのがホンネだろう。
それから、目くらましの裏に隠されている意外な真相がべつに意外でもなかった。ネタを割らない程度に事件の核心にかかわるくだりを拾ってみると、.... we will all fly to someone, we will return to that piece of shining matter from which our souls were torn with another, two halves of the same. It may be that the husband your sister has now has that other soul, that has the same affinity with her soul ....(p.210)I was only seeking you out, as you were seeking me. You were seeking me, your own affinity. .... We are the same, you and me. We have been cut, two halves, from the same piece of shining matter.(p.275)
ぼくはこうした一節を読み、反射的にロレンスのメルヴィル論を思い出した。「愛は完全であってはならない。愛には完全な瞬間があってしかるべきだが、それと同時に、茨の茂る荒野がなければならない。実際、現実でもそうなっている。『完全な』関係などというものは有ってはならない。すべての関係には、それぞれの魂の独立のために不可欠な、絶対的な限界、絶対的な制約があるべきなのだ。本当に完全な関係というのは、相手に広大な未知の領域を残しておく者にとっての関係なのだ」。(『アメリカ古典文学研究』大西直樹訳)
ロレンスの感動的なことばとくらべると、上の "Affinity" からの引用部分はなんと感傷的に聞こえることか。そこには一種の胡散くささえ感じとれる。とそんな感想が「まさか結末につながろうとはとんと気づかなかった」。気づかなかったが、一瞬でも胡散くさく思っただけに、意外な結末ではなかった。
ともあれ、これで Sarah Waters は4冊目。初めて読んだのは2006年のブッカー賞最終候補作 "The Night Watch" で、あれはほんとうに面白かった。が、再読したいとは思わない。重スミのアラさがしばかりしそうな気がするからだ。たぶん未読の旧作を読むこともないだろう。
というわけで以下、ささやかながら、Sarah Waters の既読作品一覧をアップしておこう。
1. Affinity(1999 ☆☆☆★★)
2. Fingersmith(2002 ☆☆☆★★★)
3. The Night Watch(2006 ☆☆☆☆)
4. The Little Stranger(2009 ☆☆☆)