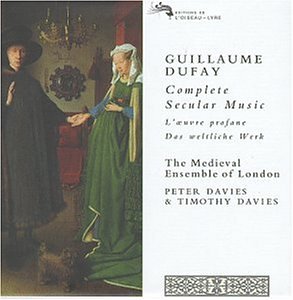Virginia Woolf の "Mrs Dalloway"(1925)をボチボチ読んでいる。年始にぼんやり立てた予定より1ヵ月遅れだ。Woolf はちょうど1年前に取り組んだ "To the Lighthouse"(1927 ☆☆☆☆★)が初見で、今回が2冊目。
同書を読んだとき、なにしろ Virginia Woolf は英文学史上でもキラ星のような作家のひとりなので、どんな経歴だったのか調べたところ、どうやら "Mrs Dalloway" がいちばんの代表作らしいと知った。以来ずっと気になっていた。
テキストは Penguin Classics。ところどころ注の番号がふってあり、面倒くさいので大半は無視しているのだけど、ときたま、どうしても後注を読まないと意味不明のくだりがある。Mrs Dalloway と久しぶりに再会した元カレの Peter Walsh が夫人の屋敷を出たあと、St. Margaret's 寺院の鐘の音を耳にした場面(注33)などだ。Mrs Dalloway を思う Peter の心理と、鐘の音という物理現象が詩的連想で溶けまじって一体化。これが裏表紙にある this book's celebrated stream of consciousness(New Yorker 誌)の一例なのかどうか、英文科の先生におうかがいしたいところだ。
まだ序盤のせいか、物語性はほとんどない。上の場面をはじめ、細部の描写に異様なこだわりがあり、鋭敏な知性と詩的感受性の発露かもしれない。
物語性の欠如といえば、表題作も相当なものだった。
大筋としては、イスタンブールに住む弁護士 Galip の妻 Rüya がある日突然、理由も告げずに家出。それと同時に、いとこの有名な新聞記者 Celal も行方不明とわかり、Galip はふたりの居所の手がかりをつかむべく、Celal の書いた膨大な量のコラムを読みかえす。ボスポラス海峡が干上がった話など、最初のうちは面白かった。
ところが、やがてどのコラム、どの逸話も似たり寄ったりで、テーマもひとつに集約されるようになる。Turks no longer wanted to be Turks, they wanted to be something else altogether ....(p.61)"We've both become different people. .... Who am I, who am I, who am I?"(p.149).... how easy it was for someone else to assume a man's identity ....(p.171).... something .... would spring up suddenly from the very depths of my soul to intone the same words over and over: I must be myself, I must be myself, I must be myself.(p.180)I know how hard it is for a person to be himself, ....(p.202)
例によって不得要領の引用だが、登場人物がだれで、どんな状況での発言かといった知識はむしろ不要。「どのコラムも同工異曲」。「アイデンティティの変容と確立をいかに表現するか、その一点に絞って無数とも思えるエピソードが積み重ねられていく」。
つまり金太郎飴のようなもので、もちろん多少の顔のちがいはあるけれど、実際は皆無にひとしい。こうなると物語性もへったくれもなく、その後、痴情のもつれがあったり殺人事件が起きたりするものの、「アイデンティティの変容と確立」というテーマは終始一貫、変わらない。
なぜ Orhan Pamuk は、これほどまでにアイデンティティの問題にこだわるのか。そう思いつつ、数ある小説の構成要素のなかでも物語性をかなり重視するぼくは、さすがに途中でヘコたれてしまった。(この項つづく)
(下は、この記事を書きながら聴いていたCD)