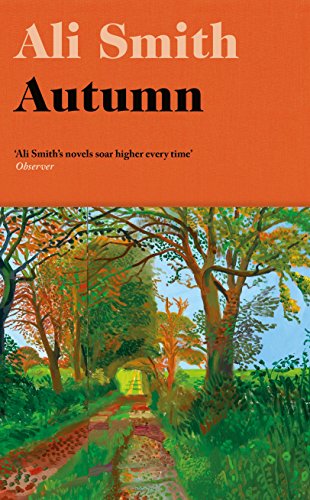今年のブッカー賞ショートリストが発表された。ぼくの予想は大はずれ。お気に入りの "Days without End" と "The Ministry of Utmost Happiness" が落選したのはとても残念だ。 今年は夏から超多忙で、未読の候補作をカバーする時間がなかった。以下の6作品のうち、レビューはいずれも再録である。(後注:"4321" と "Lincoln in the Bardo" のレビューはその後追加)。
現地ファンのあいだでは、ロングリストの発表以前から "Lincoln in the Bardo" の評価が非常に高い。昨年に引き続き、2度目のアメリカ人作家受賞ということになるかもしれません。でも、それならいっそ、"4321" のほうが個人的にはいいかな。Auster は好きな作家だから。これが対抗でしょうか。
4 3 2 1 by Paul Auster (US)
[☆☆☆★★★] 大力作のメタフィクションである。1900年、ニューヨーク港に降りたったユダヤ系ロシア移民の孫ファーガソンが少年時代から1970年まで、四とおりの人生を歩む姿を描いたSFのパラレル・ワールドに近い設定だが、単なる思いつきではなく歴とした必然性があり、仮想現実とフィクションがごく自然に融合。家族や友人、恋人たちとのふれあいがもたらす心中の葛藤は青春の嵐そのものだが、それは同時にケネディの登場と暗殺、ヴェトナム戦争と反戦運動、コロンビア大学紛争、黒人公民権運動など、60年代の大事件や政治状況とも密接にかかわっており、四者四様、それぞれ同じ激動の時代に思春期を過ごした歴史の生き証人の回顧録、壮大な「総合青春小説」に仕上がっている。なかには世界の名著名作にふれることで文学に傾斜し、学生新聞への投稿や仏詩の翻訳などを通じて創作活動をはじめるファーガソンもいて、ユダヤ系という出自や年齢も考慮すれば、これはオースターが自身の体験をフィクション化した自伝小説と位置づけることもできる。青春とはいろいろな可能性を秘めた時代であり、その可能性を四つのパターンに大別し、それぞれの流れを追いかけたもの、というのが本書のメタフィクションたるゆえんであり、『冬の日誌』『内面からの報告書』とつづいた自伝シリーズの延長線上にある総決算的な小説ともいえよう。それゆえこの膨大な量となったわけだが、残念ながら力作どまり、傑作とは評しかねる。四とおりの人生、四つの可能性は示されても、四つの価値観が提出されているわけではないからだ。意見の相違は、たとえばヴェトナム戦争をめぐるものなど、あくまで外的・政治的な次元にとどまり、四人のファーガソンがそれぞれ異なる人生観・世界観を有して内的・精神的に激突するわけではない。酷評すれば四人とも似たり寄ったり。それなら、これほどの紙幅を費やしてパラレル・ワールドを構築するまでもなかったのではないか、ということになる。自伝小説ゆえの限界かもしれないが、巨匠オースターにはその限界を超えて欲しかった。それが超えられなかったところに彼の限界があるということか。(11月12日)History of Wolves by Emily Fridlund (US)
Exit West by Mohsin Hamid (Pakistan-UK)
[☆☆☆★] いまや先進国の移民問題には、適切な解決策はないのかもしれない。本書は近未来のSF的な設定により、移民と先住民の対立を先鋭化させることで、現代の深刻な状況を浮き彫りにしたものである。ある無名の街に突然出現したドアを抜けると、ドバイへ、ロンドンへ、サンフランシスコへと瞬時に移動。政府軍と過激派の戦闘が絶えない街から、恋人たちは安住の地を求めて必死の脱出劇を繰りひろげる。それがサスペンスに満ちて快調そのものだ。大量の移民流入によりイギリスは極度の分裂状態、虐殺の危機が迫り、正義の意味が問われる一方、当初は仲むつまじかったふたりにも不協和音が生じる。こうした不穏な情勢と不安な心理のコントラストはとても鮮やかで座布団一枚。が、シスコへ飛んだあたりから少々散漫な展開になる。愛する者との別れを経験し、喪失の悲しみを共有することで、立場の異なる人びとの絆が深まるという指摘は傾聴に値するものの、むろん移民問題の抜本的な解決にはならない。祈ることしかできないという嘆きも当たり前。そんな状況で恋人たちの関係がどうなるかも知れたこと。快調な滑りだしだっただけに、うやむやな結末に不満がつのる。(6月19日)Elmet by Fiona Mozley (UK)
Lincoln in the Bardo by George Saunders (US)
[☆☆☆★★★] 実験的な、あまりに実験的なゴースト・ストーリーである。複数の話者の発言を引用しながらリレー方式で同じひとつのシークエンスを叙述。非日常的な口語や俗語、造語、破格構文などを駆使。意識の流れに近い技法や、はたまた「意識の途切れ」とでもいうべき表現まで続出するありさまたるや、言語芸術としての文学、ここにきわまれり。まさに爆発的なことばの乱舞である。しかもその話者は大半が亡霊であり、数多くの亡霊たちが生者に憑依したのち離脱、ハチャメチャな暴動を起こしたり、エロっぽいドタバタを演じたり、とにかく猥雑な一大狂騒劇を繰りひろげる点で、これはマジックリアリズムの極北ともいえる作品である。が、こうした超絶技巧のわりに、テーマとしては意外に底が浅い。肉親に先だたれた家族の悲しみ、死にゆく者の嘆き。これらはギリシア悲劇の時代から扱われてきた題材である。むろん本書の場合、南北戦争当時、リンカーンが幼い息子を病気で亡くしたという小さな史実から、これほど破天荒なドラマを仕上げた点は高く評価できる。生と死の中間領域(チベット仏教のバルド)を援用したところも画期的。しかしながら、要するに死とは悲惨なもの、というテーマしか見えてこないがゆえに「底が浅い」。こと南北戦争にかんする記述にしぼっても、たとえばロバート・ペン・ウォーレンの名著『南北戦争の遺産』とは雲泥の差である。また一方、言語芸術としての文学における実験を試みた先達の作品とくらべても見劣りがする。「死とは悲惨なもの」というだけの認識からは、ジョイスの世界観、フォークナーの人間観に伍するような深いヴィジョンを読みとることはできない。とすれば、「ことばの乱舞」にいかほどの意味があろう。などなど減点材料は多々あるものの、ひるがえって饒舌なナンセンスとは、ひとりジョージ・ソーンダーズのみならず、現代作家の通弊ともいえる欠陥かもしれぬ。その意味で本書は、現代文学の極北を示した作品でもある。(12月16日)Autumn by Ali Smith (UK)
[☆☆☆★★] スコットランド独立や、移民の増大、EU離脱など、国論を二分する問題でゆれ動くイギリス。かつての大英帝国の栄光は残滓すらとうに消え、いまや冬の時代を迎えつつあるかもしれぬ時期、つまり秋。本書に散見されるイギリス現代社会への風刺は、そうした〈秋の時代〉を描いたものだろう。このとき、百歳を超えた老人ダニエルが療養所でこんこんと眠りつづけている。そのダニエルを足繁く見舞う若い女エリザベス。本書は、エリザベスの幼い娘時代にはじまるふたりの交流と、混乱に満ちた現代、さらには、美術史専門の学者である現在の彼女がとらえた1960年代の状況を織りまぜ、駆け足でイギリスの最近50年史を総括した作品である。少女と老人のふれあいはハートウォーミング。お役所仕事にキレた女の奮闘ぶりはユーモラス。ポップアートの説明はリズミカル。三つあわせて文学的コラージュそのものといえよう。最後、冬の初めに咲いた美しいバラは、作者が祖国にたいしていだく、かすかな希望を象徴しているのかもしれない。(12月24日)