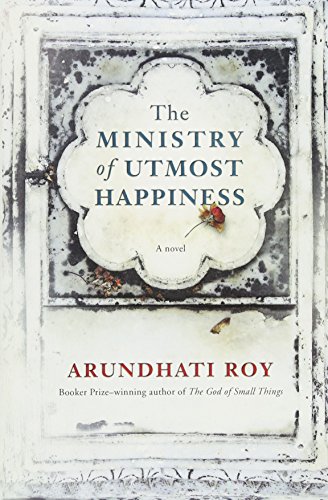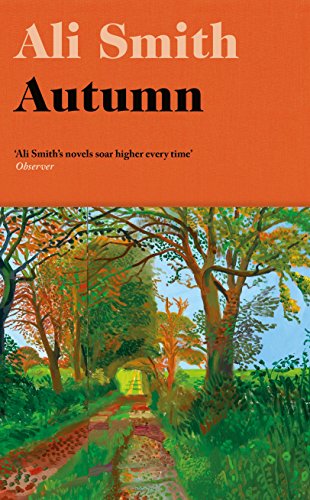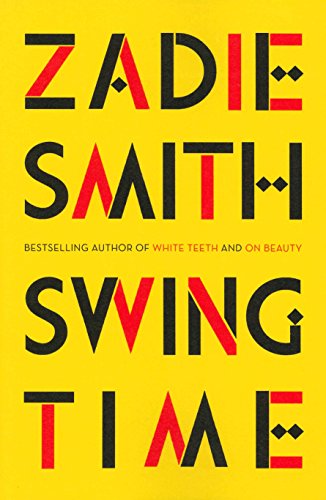今年のブッカー賞ロングリストが発表された。このうち、"The Underground Railroad" はご存じのとおり、今年のピューリッツァー賞、および昨年の全米図書賞の受賞作でもある。また、"Days without End" は今年のコスタ賞大賞受賞作。両作品をふくめ、ぼくが読んだことのあるのは5冊だけ(その後2冊通読)。
全13冊の顔ぶれを見ると、現地ファンのあいだで下馬評に上がっていた作品が多いようだ。希望混じりのヤマカンだが、"Days without End" と "The Ministry of Utmost Happiness" はショートリスト入りの可能性が高いと思う。以下、5冊のレビューを再録しておこう(その後2本追加)。
4 3 2 1 by Paul Auster (US)
Days Without End by Sebastian Barry (Ireland) [☆☆☆★★★] 殺すか殺されるか。ひとりの命を救うために、もうひとりの命を奪わねばならぬときにどうするか。本書は、人間がそういう究極の選択を迫られる限界状況をみごとにドラマ化した作品である。19世紀なかば、アイルランドから渡米した少年トマスが、親友のジョンともども酒場のミンストレル・ショーに女装で出演するなど、滑りだしはコミカルで陽気。しかしやがてふたりは陸軍に入隊、自然の猛威と戦ううちにインディアンと遭遇し、激しい戦闘がはじまる。勧善懲悪とは無縁のリアルな西部劇である。それが一段落したあと、こんどは南北戦争勃発。息づまるような白兵戦をはじめ、悲惨な戦争の現実が生々しく描かれる。ゆえにこれが最大の山場と思いきや、戦後なんと、さらに恐るべき修羅場が待っていた。映画でおなじみの無法者たちとの決闘シーンに固唾をのみ、ついでふたたびインディアンとの戦闘開始。いまや伍長のトマスは人生最大の選択をしいられる破目に。序盤から数かずのアクション・シーンを経て次第に高まってきた緊張が一気に沸点に達する瞬間であり、と同時に、上記の女装もこの極限へとつながる布石だったことがわかる。すこぶる巧みな構成で、ただもう驚くばかり。しかもこのとき、人間の善良さと残虐さが等しく浮き彫りにされ、また、神ならぬ人間には不完全な答えしか選べないという人生の苦い真実も読みとれる。善悪の彼岸にある、まさしく「リアルな西部劇」である。
History of Wolves by Emily Fridlund (US) Exit West by Mohsin Hamid (Pakistan-UK) [☆☆☆★] いまや先進国の移民問題には、適切な解決策はないのかもしれない。本書は近未来のSF的な設定により、移民と先住民の対立を先鋭化させることで、現代の深刻な状況を浮き彫りにしたものである。街なかに突然出現したドアを抜けると、ドバイへ、ロンドンへ、サンフランシスコへと瞬時に移動。政府軍と過激派の戦闘が絶えない街を出発点に、恋人たちは安住の地を求めて必死の脱出劇を繰りひろげる。このロンドン編まではサスペンスに満ちておもしろい。大量の移民流入により国家は分裂状態、虐殺の危機が迫り、正義の意味が問われる一方、当初は仲むつまじかった二人にも不協和音が生じる。こうした不穏な情勢と不安な心理のコントラストはとても鮮やかで座布団一枚。が、シスコへ飛んだあたりから少々散漫な展開になる。愛する者との別れ、喪失の悲しみを共有することで絆が深まるという指摘は傾聴に値するものの、もちろん移民問題の抜本的な解決にはつながらない。祈ることしかできないという嘆きも当たり前。そんな状況で二人の関係がどうなるかも知れたこと。快調な滑り出しだっただけに、うやむやな結末に不満がつのる。
Solar Bones by Mike McCormack (Ireland) Reservoir 13 by Jon McGregor (UK)Elmet by Fiona Mozley (UK) The Ministry Of Utmost Happiness by Arundhati Roy (India) [☆☆☆★★★] インド的な、あまりにもインド的な力作である。多民族、多宗教、多言語の大国インド。現実には四分五裂しながらも国家としての統一性を保持するという矛盾。その矛盾を矛盾のままに描き、悲哀に満ちた混沌のなかから希望の光を見いだそうとする試みが本書である。開巻早々、男でも女でもない「中性」のアンジュムがデリー市内の墓場に住んでいるという設定からして矛盾の象徴だ。やがてアンジュムの拾った捨て子が何者かにさらわれ、その意味も不明のまま、こんどはカシミール問題をめぐり、インド情報部の高官と一流ジャーナリスト、ムジャヒディンの戦士が三者三様、複雑に絡みあう。彼らをお互いに結びつけているのは友情であり、そして三人が愛したひとりの女だが、その全貌は中盤過ぎまで杳として知れない。悠々たるインダスの流れのごとく、話はなかなか先へ進まない。これは相当に忍耐を要する作品である。が、その努力は後半で報われる。一見ランダムにちりばめられていたパズルのピースが少しずつ絵柄となり、やがて恋あり冒険あり、時にはスパイ小説の味わいも楽しめるほど手に汗握る展開だ。ひと息ついたところで舞台はふたたびデリーの墓場。過激なナショナリズムや原理主義など、依然として危険と不安の要素がつきまとうインドの現代にあって、アンジュムの育てる幼い子どもの姿に明るい未来が託され、最大の幸福への願いが込められているのである。
Lincoln in the Bardo by George Saunders (US) [☆☆☆★★★] 実験的な、あまりに実験的なゴースト・ストーリーである。複数の話者の発言を引用しながらリレー方式で同じひとつのシークエンスを叙述。非日常的な口語や俗語、造語、破格構文などを駆使。意識の流れに近い技法や、はたまた「意識の途切れ」とでもいうような表現までも続出するありさまたるや、言語芸術としての文学、ここに極まれり。まさに爆発的な言葉の乱舞である。しかもその話者は大半が亡霊であり、数多くの亡霊たちが生者に憑依しては離脱、ハチャメチャな暴動を起こしたり、エロっぽいドタバタを演じたり、とにかく猥雑な一大狂騒劇を繰りひろげるのだから、マジックリアリズムの極北とも言える作品である。が、こうした超絶的な技巧のわりに、テーマとしては意外に底が浅い。肉親に先立たれた家族の悲しみ、死にゆく者の嘆き。これらはギリシャ悲劇の時代から扱われてきた題材である。むろん本書の場合、南北戦争当時、リンカーンが幼い息子を病気で失ったという小さな史実から、これほど破天荒なドラマを仕上げた点は高く評価したい。生と死の中間領域を開拓しているところも画期的。しかしながら、要するに死とは悲惨なもの、というテーマしか見えてこないがゆえに「底が浅い」。こと南北戦争にかんする記述に絞っても、たとえばロバート・ペン・ウォーレンの名著『南北戦争の遺産』とは雲泥の差である。また一方、言語芸術としての文学における新しい実験を試みた先達の作品とくらべても大いに見劣りがする。「死とは悲惨なもの」というだけの認識からは、ジョイスの世界観、フォークナーの人間観に伍するような深いヴィジョンを読み取ることはできない。とすれば、「言葉の乱舞」にいかほどの意味があるのだろう。などなど減点材料は多々あるのだが、ひるがえって饒舌なナンセンスとは、ひとりジョージ・ソーンダーズのみならず、現代作家の通弊とも言える欠陥かもしれない。その意味で本書は、現代文学の極北を示した作品でもある。(12月16日)
Home Fire by Kamila Shamsie (UK-Pakistan) Autumn by Ali Smith (UK) [☆☆☆★★] スコットランド独立や、移民の増大、EU離脱など、国論を二分する問題でゆれ動くイギリス。かつての大英帝国の栄光は残滓すらとうに消え、いまや冬の時代を迎えつつあるかもしれぬ時期、つまり秋。本書に散見されるイギリス現代社会への風刺は、そうした〈秋の時代〉を描いたものだろう。このとき、百歳を超えた老人ダニエルが療養所でこんこんと眠りつづけている。そのダニエルを足繁く見舞う若い女エリザベス。本書は、エリザベスの幼い娘時代にはじまるふたりの交流と、混乱に満ちた現代、さらには、美術史専門の学者である現在の彼女がとらえた1960年代の状況を織りまぜ、駆け足でイギリスの最近50年史を総括した作品である。少女と老人のふれあいはハートウォーミング。お役所仕事にキレた女の奮闘ぶりはユーモラス。ポップアートの説明はリズミカル。三つあわせて文学的コラージュそのものといえよう。最後、冬の初めに咲いた美しいバラは、作者が祖国にたいしていだく、かすかな希望を象徴しているのかもしれない。
Swing Time by Zadie Smith (UK) The Underground Railroad by Colson Whitehead (US) [☆☆☆★★] アメリカの奴隷制といえば、芸術作品のテーマとしては相当に古い。差別問題ともども、映画や小説の中で長らく語り継がれ、いまや歴とした伝統文化の一翼を担う素材となっている。その長い歴史に新たな1ページを刻むとすれば、新しい真実の発掘とはいわないまでも、斬新な角度からの取り組み、新工夫が必要だろう。その点、本書はいちおう合格ラインをクリア。従来あまり描かれることのなかった逃亡奴隷に焦点を当て、賞金稼ぎとのあいだに繰りひろげられる、追いつ追われつの逃亡劇に仕上がっている。が、何よりその逃走手段が斬新でユニークだ。現実と幻想のはざまに敷かれた地下鉄道は、隷属から自由へいたる道として、国家の存立基盤、国民のアイデンティティを再確認させるものと想像する。さほどに奴隷制は、人種差別はアメリカ人の心の宿痾ということだろうが、ひるがえって、ここには再確認こそあっても新発見はない。メルヴィルやフォークナーなど、アメリカの最高の知性が産み出してきた伝統文化に加えるものはほとんど何もない。人間を単純に善玉と悪玉に分けるのではなく、知的に誠実であること。このメルヴィルの原点に立ち返ってこそ、もはや語り尽くされた感のあるテーマでも真に新しい物語を作れるのではないか、と愚考する次第である。