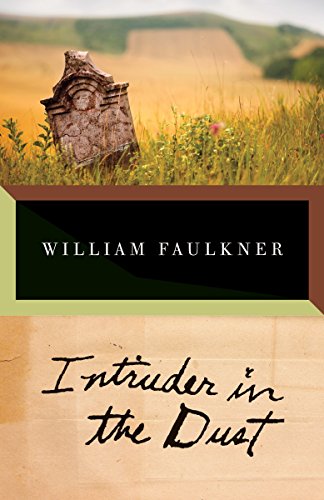William Faulkner の "Intruder in the Dust" をやっと読了。これほどの難物は久しぶりだった。
追記:本書は1949年に映画化されましたが、日本では未公開のようです。
チックと同様、フォークナーは逃避を拒んだ作家である。例によって本書でも、ヨクナパトーファ郡の歴史や地理、風土、住民、その特徴などが、見方によっては冗漫と言えるほど緻密な文体で紹介されているが、その目的の一つは、少なくとも南部人が持っている黒人差別意識を、動物的本能というより、人間存在の根底にしみついているような意味での本能として描きだすことにある。その結果、差別意識は単にアメリカの一地方にとどまらず、人間全体にかかわる問題となる。
「存在の根底」とは観念的な表現だが、フォークナーの手法は決して哲学者のものではなく、「冗漫と言えるほど緻密な文体」にもとづく、まさしく小説家独特のアプローチである。それゆえ、読者はいわば理屈ぬきに、自分の「内なる差別意識」を意識せざるを得ない。そういう説得力は結局、フォークナーもまた、創作を通じて自身の内面を見つめ続けたからこそ生まれるものではないだろうか。人間に本質的な差別意識があることを追求している点で、フォークナーは内なる現実から逃避しなかった作家である。
差別意識とは負の現実である。だが、フォークナーはその現実を直視する一方、本書で「誇り高き少年を主人公に据えている」。それどころか、相手の黒人もプライドが高いし、少年を助ける弁護士の伯父や、少年の母も、墓堀りを手伝う老婦人も、いざとなると毅然とした態度で困難に立ち向かう。こういう各人物の示す誇りが、本書を読んで得られるカタルシスにつながっている。
上のレビューを繰り返そう。「黒人が黒人らしく卑屈に振る舞わないことに苛立つ一方、黒人が不当に扱われる現実を目の当たりにして座視することもできない、座視すれば人間としての誇りをうしなうことになる
」。少年の心の中では、差別意識と「人間の誇り」はなんら矛盾していない。現実を現実として認めながら、それに埋没することなく、矜持を持って現実に対処するのが少年の生き方なのだ。
このような複眼思考というか二元論に立脚しているがゆえに、フォークナーはやはり偉大な文学者なのである。同じノーベル賞作家でも、「安手のヒューマニズム」を売り物にするどこかの国の作家とは大違いだ。しかもその作家は、「フォークナーの多大な影響を受けている」という話だが、彼はいったいフォークナーの何を学んだのだろうか。
…とまあ、壮大な誤読をしてしまったかもしれないが、この『墓地への侵入者』(48)に関しては、ほかにもまだ書きたいことがある。長くなったので、今日はこのくらいにしておこう。