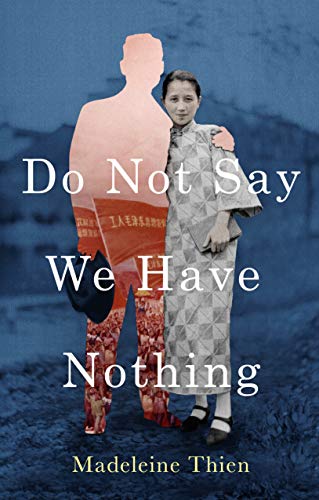今年のブッカー賞ショートリストが発表された。(この情報は、ぼくのアンテナに掲載している The Mookse and the Gripes で入手。公式発表以前の速報かもしれない。この記事も実際は13日に書きました)。本ブログに掲載した予想のうち、的中したのは "The Sellout"、"Hot Milk"、"All That Man Is" の3冊。ヤマカンにしてはよく当たったほうかな。以下、既読のものはレビューを再録しておこう。
1. Paul Beatty (US): The Sellout
2. Deborah Levy (UK): Hot Milk[☆☆☆★★★] ここには感動はたぶん、ない。自分が自分を見うしない、自分ではないものに縛られ、自分を愛しているはずの人間、自分自身が愛しているはずの人間との関係があやうい若い女。介護が必要な母の治療のために訪れた南スペインの海辺で、母と別れた父の住むギリシャの街で、彼女は考える。迷う。自分とは、自分の人生とは、愛とはいったい何なのだろう。ゆれ動く微妙な心理が静かな、しかし鮮やかなショットで風景に映しだされる。出会った男たち、女たちとのふれあいのなかで劇的な事件が起こり、感情が高まり、落ち込み、また爆発し、純化される。本書はそうした濃密な心象風景を、さまざまな思いの去来する一瞬の情景を楽しむ本である。それを絶妙かつ的確にとらえた繊細なタッチに読みほれてしまう。かりそめの中途半端な人生、あいまいで不確かな現実を象徴するエピソードが連続する。と、ふと行間に目をとめ、自分自身の人生をふりかえりたくなるかもしれない。そこにも感動はないかもしれない。が、心に浮かぶ風景ならきっとあるはずだ。本書は、ヒロインに共感できれば、そうした記憶の引き金になるような作品である。(8月28日)
3. Graeme Macrae Burnet (UK): His Bloody Project[☆☆☆★] よく出来たクライム・ストーリー。19世紀なかば、スコットランドのハイランド地方で凄惨な殺人事件が起こる。犯人の少年はあっさり犯行を自供するが、犯行時、彼は正気だったのか否か。前半、事件の背景と犯行までの経緯を物語る少年の回想録は青春小説の味わいもあり、素朴なユーモアが楽しい。それが一転、凶行におよぶというコントラストが鮮やかだ。後半はリーガル・サスペンス。被告の責任能力の有無が争点だが、検察側が被害者の横暴ぶりを証明し、弁護側が少年の狂気を訴えるという皮肉な展開になっている点がおもしろい。権威主義的な上流階級への風刺も鋭い。一見単純な事件でも真相は藪の中。また神ならぬ人間の裁きに完璧は期しがたく、あってはならない誤審の可能性がつきまとう、といった人生の苦い真実も汲みとれる点を評価したい。(10月20日)
4. Ottessa Moshfegh (US): Eileen[☆☆☆★] なるほど、これはやっぱり青春小説だったか、と最後に納得。しかも通過儀礼というおなじみのテーマである。途中、それをほとんど忘れさせてしまうほど巧みなストーリー・テリングがすばらしい。老婦人のアイリーンが半世紀も昔、ニューイングランドの田舎町で過ごした最後の日々を回想する。何やら大事件が起きたらしい。それはいったい何か。この興味だけで終盤まで引っ張るとは恐れ入る。しかも事件の輪郭さえつかめない。娘時代のアイリーンをはじめ、アル中の父親、彼女が勤めていた少年院の同僚など、顔を出すのは性格・感情ともに単純化された人物ばかり。それだけに彼らが極端な言動に走っても説得力があり、小さなエピソードの混ぜ具合もうまく、つい話の流れに乗せられてしまう。次第に盛り上がるサスペンスもおみごと。これならさぞ衝撃的な事件が待っているはず。実際、それは衝撃的である。が、その真相を知ったからといって得るものは何もない。要するに青春の嵐だったというだけだ。尋常ならざる嵐ではあるが、通過儀礼のわりに共感できないぶん損をしている。(9月30日)
5. David Szalay (Canada-UK): All That Man Is [☆☆☆★★★] 形式的にはナイン・ストーリーズ。いや実質的にも短編集だが、もしこれを長編と考えるなら、主人公はタイトルどおり「男」。17才の少年から70過ぎの老人まで、9人の男がリレー方式で次第に年齢を上げながらイギリスからクロアチアまで、ヨーロッパ各地で男ならではの人生を歩む。青春の挫折、喪失と苦悩、女とのすれちがい、私情と仕事の板ばさみ、迫られた選択、事業の失敗、迫りくる死。男がいつかはどこかで必ず経験する人生の厳しい局面が、時にユーモアをまじえながらほろ苦く、あるいは張り詰めた空気のなかで重苦しく、それぞれの場面にふさわしい筆致で描かれる。よかれあしかれ、泣いても笑っても、これが男の人生なのだ、というわけである。と同時に、人生は冗談ごとではない、というメッセージも読みとれ、そしてなにより鋭い感覚で一瞬、心のひだを、人間存在の現実をとらえたものという意味で、これはけっして性差別小説ではない。人生の過ぎゆく時間を、ひとつひとつの瞬間を永遠の流れのなかに定着させようとする試みともいえよう。作者は、人生のはかなさと永遠性を同時に見つめている。これはその葛藤から生まれた短編集にして長編小説である。(9月6日)
6. Madeleine Thien (Canada): Do Not Say We Have Nothing[☆☆☆★★★] 政治と音楽を対位法的にとらえた重厚な大河歴史小説。主旋律のひとつは、文化大革命と天安門事件を頂点とする激動の中国現代史だ。正義という名の粛清、大衆ヒステリー、公開リンチ、そして暴力、殺戮、大衆弾圧。全体主義の恐怖が劇的かつ臨場感たっぷりに描かれる。タイトルは中国版『インターナショナル』の英訳歌詞の一節で、これを歌いながら人民が人民解放軍に立ち向かうところに痛烈な風刺が読み取れる。どのエピソードも史実にヒントを得たものなら歴史小説だが、中国当局の主張が正しければディストピア小説。いずれにしても、正義から圧政、殺人にいたる過程はドストエフスキーの『悪霊』と軌を一にしている。もうひとつの主旋律は音楽だ。上の事件に巻き込まれるのが三人の音楽家とその家族とあって、音楽の話題は常に政治と平行して進む。真の音楽は作曲家の魂から生まれ、演奏家の霊感を通じてリスナーの心に直裁に響いてくる。こうした音楽の特性はまさしく自由そのものであり、本来、イデオロギーの及ぶところではない。それを政治の現実と対峙させることにより、自由と圧政という対位法も生まれている。おなじみのテーマだが、それを音楽家たちの人生および国家の歴史としてフィクション化した点がすばらしい。大変な力作である。(10月14日)