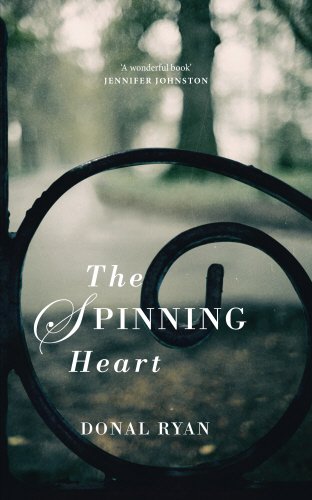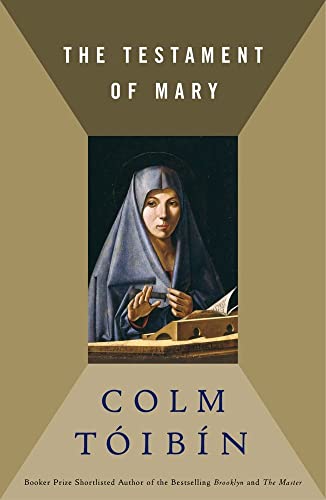いよいよロンドン時間で23日、ブッカー賞のロングリストが発表される。あちらのファンはさぞ、どんな作品が選ばれそうかという話題で大いに盛り上がっていることだろう。
下馬評の一部は、このブログで紹介している Man Booker Prize Eligible 2013 や The Mookse and the Gripes Forum などで確認することができる。中にはたまたま以前に読んでいたものもあるが、最近はぼくも2つのサイトを参考に何冊か読んできた。
そこできょうは、およそ貧弱なリストで看板に偽りありだが、いままで読んだ今年の「ロングリスト有資格作品」のレビューを、ぼくが有望と思っている順に再録しておこう。なお、Chimamanda Ngozi Adichie の "Americanah" だけは、ちょうどいま読んでいる最中なので、点数は暫定評価です。(追記:7月25日に "Americanah" のレビューを発表。点数を確定しました)。
[☆☆☆☆] なるほど、この手があったか、と感心した。
アメリカにおける人種差別という文学的には古びたテーマを、みごとに現代的に処理しているからだ。
オバマが黒人初の
アメリカ大統領となった当時、ナイジェリアから渡米した
若い女イフェメルがブログを開設し、日常生活で体験した差別や
差別意識の現実をユーモアたっぷりに報告。そのブログ記事と前後して、もっぱら仕事や恋愛における彼女の悪戦苦闘ぶりも客観的に描かれる。こうした二重の叙述形式が「この手」なのだ。このいわば複眼によるイフェメルの観察の結果、単眼の場合以上に差別の実態がまざまざと浮かびあがっている。がしかし、本書のテーマは差別にとどまらない。男と別れブログも閉鎖、長い渡米生活をおえて帰国を決意したイフェメルは娘時代からの人生を回想。それがおわるとこんどは現在進行形の物語がはじまる。妥協を拒み、自分の意見をはっきり述べる女性がどんな試練に出会い、どのように成長していったか。その大きな流れのなかで差別の問題もとらえるべきだ。存在感あふれる各人物、微妙な心理、複雑な人間関係、情感のこもった一瞬の光景など、どの描写も的確ですばらしい。それゆえ終盤、意外に平凡なメロドラマとなっても気にならない。ナイジェリア版『
女の一生』、ただし、まだまだつづく人生物語である。
[☆☆☆★★] まず着想がいい。タイトルどおり、あるアジアの国、おそらく
パキスタンで金持ちになるためのノウハウが各章の冒頭で示されたあと、次いで主人公の男が各ステップを実践。それがそのまま男の人生を象徴する場面となり、ひいては貧困や混乱など、彼の住む社会全体の状況を端的に物語るものとなっている。ふつうに書けば、おもしろくも何ともない人生かもしれない。貧しい村で生まれた男が都会に出て悪戦苦闘の末に財を成し、さらに紆余曲折を経たのち、年老いて死んでいく。要はそれだけの話が蓄財術にかこつけて語られるや、じつに芳醇な小説的香りを放つようになる。ユーモラスなエピソードが多く、時に身の危険にかかわる緊張が走り、ふと哀愁を帯び、ハートウォーミングで、しみじみとした情感がこもる。とりわけ、男が少年時代に恋をした女の子の物語が泣かせる。出会いと別れ、すれちがい、再会。このテーマが全編にわたって
通奏低音のように流れ、男の人生の節目節目に主旋律となる。ひるがえって、タイトルに直結した立身出世編のほうはスケールが小さく、紆余曲折はあるものの常識的な展開になっている点が惜しい。英語は歯切れよくエネルギッシュな文体で、入り組んだ箇所もあるが、総じて標準的で読みやすい。
[☆☆☆★★] 哲学とは「ひとを揺さぶり、ひとの人生を変えるようなもの」であるのが望ましい、と主人公の中年男シモンはいう。ところが、ここで頻繁に出てくる哲学的議論から深い感動をおぼえることはまずない。それが本書の最大の難点である。とはいえ、SFの
未来社会のような街で繰りひろげられる物語はかなりおもしろい。シモンと、彼が街に連れてきた少年ダ
ビード。その母親だとシモンが決めつけ、やがて自分もその気になる女イネス。どれも本名ではなく、それぞれ赤の他人だが、三人は紆余曲折のすえ奇妙な家族を形成する。ほかにも、過去を捨てた人間たちが集まる新都市ゆえに、システムとしては能率的だが、無機的で希薄な関係しか結べない社会にあって、偶然の出会いからさまざまな人的交流がはじまる。明らかに現代の世相を反映した寓話といえよう。シモンとダ
ビードの問答を通じて、既存の体制内では異端者だが、真実を洞察して人びとに訴え、それゆえ迫害を受けたイ
エスの立場が思い出される。タイトルどおり一種の聖書物語らしいくだりである。が、その問答をはじめ、本書における哲学論は、人生の目的をテーマにしたものでさえ抽象的で心にひびいてこない。倫理や道徳にかかわる問題がいっさい無視されているからだ。ダ
ビードもおよそイ
エスらしくない駄々っ子である。物語をひねりすぎたのではないだろうか。
[☆☆☆★★] 舞台はイギリスの片田舎。まだ
荘園領主が村を治めていた時代、不心得者が領主の館で失火騒ぎを起こし、それきっかけに悲劇がはじまる。深読みかもしれないが、これは
現代社会に警鐘を鳴らした寓話小説と解することもできよう。どんなに平和で繁栄した国でも、
不都合な真実を隠蔽するうちに混乱が生じ、最悪の場合には社会全体が崩壊してしまう。その過程にはさまざまな負の連鎖がある。真実の隠蔽はもちろん、縄張り意識と差別、大衆への迎合、集団ヒステリー、
魔女狩り、
ユートピアの欺瞞、権力者の恣意と優柔不断、権力の空白がもたらす無秩序、正義感に駆られた人間のふるう暴力。当初はのどかな田園風景にふさわしいゆるやかな展開で、しかも上のもろもろの要素が複雑にからまり、なかなか話の方向が見えない。しかしやがて事件がしだいに
エスカレート。気づいたときには主人公ともども、地域社会の崩壊を目のあたりにしている。それはいわば複合現象であり、どれかひとつが決定的な要因とはいいがたい。そのぶん焦点がぼやけ、
インパクトに欠ける憾みもあるが、こうした負の連鎖こそ、じつはすこぶる現代的な崩壊過程ではないだろうか。
[☆☆☆★]
アイルランドの小さな村を舞台とする、実質的には
ショートショート集といってもいい輪舞形式の長編。短い生活スケッチ風の物語の中で、さまざまな人物の独白が連続するうちに、第1話に登場する建築業者ボビーの人生が浮かびあがる。テーマは大ざっぱにいえば生と死、そして愛。親子や兄弟など肉親の死がたびたび話題となり、見かけとは裏腹に、激しい憎しみや恨みもふくめた各人の心中に渦巻く感情が赤裸々に綴られる。この表面と深層心理の落差、および愛憎なかばする心の動きを描くには、視点が目まぐるしく変化する輪舞形式は最適の方法のひとつかもしれない。「回転する心」とはまさに言い得て妙のタイトルである。人は生きていくうちに、何度かつらく悲しい出来事に出会うが、それも生きていればこその話だ。同様に、人は人を愛するうちに憎しみ、それがまた愛する意味にもなる。そんな当たり前のことを思い出すシーンに胸をえぐられる。ただし、後半に起きる子供の誘拐事件は蛇足。逆にこれがないと単調になるものの、結果的にいわば「心が回転しすぎてしまった」のが惜しい。英語は俗語や方言などブロークンな口語表現が続出し、現代の作品としてはむずかしめである。
[☆☆☆★] 自分の生きている現実以外に、またべつの現実が存在するかもしれない。本書はこの、SFでおなじみの
パラレルワールドの考えを自在に活用した歴史ロマン小説である。たしかに死んだはずのヒロイン、アーシュラたちが、その後なぜか、異なる状況のもとでしっかり生きている。なんの合理的な説明もないまま進む展開に当初は面食らうが、これが
パラレルワールドだと理解すれば、矛盾や曖昧な点があるのは当たり前。アーシュラがレイプされたり、されなかったり、異常な性格の夫と結婚したり、しなかったり、それぞれのエピソードを理屈ぬきに楽しめばよいということになる。極めつけは、第二次大戦中のアーシュラの戦争体験だ。ドイツ人と結婚し、ベルリンで米英軍による空襲に遭ったかと思うと、こんどはロンドンで連日連夜、ドイツ軍による大空襲。とりわけ、後者には相当な紙幅が割かれ、本書の山場となっている。が、いくら戦争の悲惨さが強調されても、しょせん複数の現実のひとつである以上、生か死かという限界状況ならではの緊迫感に欠ける憾みがある。それより何より、
パラレルワールドを提出することで、作者が何を訴えようとしているのか判然としない。実際はひとつしかない現実だからこそ、その中で生き、苦しむことにも意味があるはずだが、複数の現実のもとでは、その意味にどんな変化が生じるのか、という点がまったくふれられていない。着想はおもしろいし、個々のエピソードもそれなりに楽しめる。が、肝腎な問題が素どおりであるため、心に響いてくるものは少ない。英語は難語も散見されるが、総じて標準的なもので読みやすい。
[☆☆☆] 聖書における
聖母マリアの記述は非常に少なく、さらに、その心情を綴ったものとなると皆無。本書はそんな「歴史の空白」を埋めるべく書かれた聖書の番外編。キリストの死後何年もたったあと、死期を悟ったマリアが生前のキリストと処刑前後の出来事を回想する。子供に愛情をそそぎ、その身を案じ、子供を亡くして悲嘆にくれる母親マリア。恐怖におののき、何よりわが身の安全を考えるという人間的な弱ささえ露呈する。マリアも聖母である前に、ごくふつうの母親、ふつうの人間だったのだという解釈である。真偽のほどはさておき、キリストの処刑といえば世界史上最大の事件のひとつのはずなのに、本書からはその衝撃がさっぱり伝わってこない。「聖書の番外編」といっても、実際はすべて小さな
ホームドラマと化している。マリアに母親としての苦悩があったことは想像に難くないが、神の子イ
エスから宗教的感化を受けることはまったくなかったのだろうか。もし受けたとすれば、それは人間的苦悩にどんな変化を与えたのだろう。ト
ビーンほどの大家なら、そのあたりの葛藤をじっくり描くこともできたろうに、本書のマリア像はいかにも平板。どだい中編小説で扱うべきテーマではなかったのではないか。英語はト
ビーンらしい繊細なタッチの名文で読みやすい。