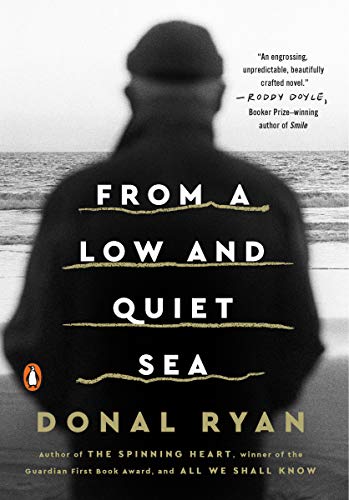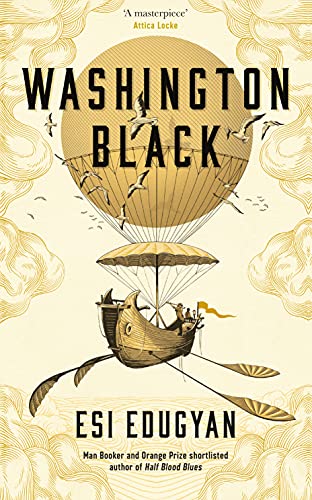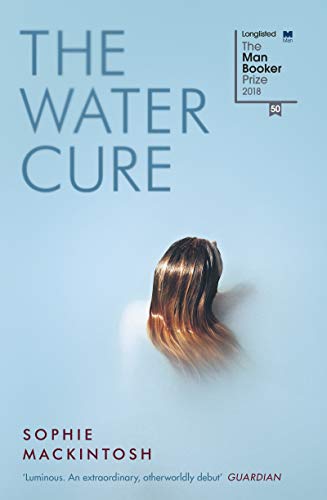ロンドン時間で24日、ブッカー賞のロングリストが発表された。ゴールデン・ブッカー賞との2冠達成か、と期待される Michale Ondaatje はやはり入選。話題づくりでしょうかね。
個人的にうれしかったのは、現地ファンの下馬評を頼りにあらかじめ読んでいた Richard Powers と Donal Ryan が入選したこと。Ryan 作品は2013年に入賞した "The Spinning Heart"(☆☆☆★)より格段にいい。また、Powers はショートリスト入りも濃厚だと思う。
上記3人のほか、発表直後のファンの予想としては、Rachel Kushner も有力視されている。あ、それから Esi Edugyan の名前を見かけるのは、2011年の最終候補作 "Half Blood Blues"(☆☆☆★★)以来。ぼくも Ondaatje、Kushner くらいは読んでみようかな。以下、Powers と Ryan のレビューを再録しておきます。
8月2日追記:ほかの候補作も読了次第、レビューを掲載。その際、ランキングを番号順で示すことにしました。
8月21日追記:ランキングは随時変更しています。
9月11日追記:ランキングを確定しました。未読の3作品については、ショートリストに入選すれば、読後にレビューを掲載する予定です。
12月14日追記:"Washington Black" のレビューを追加しました。読みのこした2作はパス。これで最終的なランキング確定です。
1."The Overstory" Richard Powers (USA)
2."Milkman" Anna Burns (UK)[☆☆☆★★★] 多くの人々が誤情報や偽情報を真実と見なし、虚報にもとづいて人格攻撃や魔女狩りに走る。本書は、そんな情報化社会における大衆ヒステリーの危険をアレゴリカルに描いた力作である。舞台は1970年代のおそらくベルファスト。警察とテロリストが動静を探りあい、親英派と反英派の住民が対立している。そうした政治状況を認識しながらコミットメントを避けていた若い娘にストーカーが近づくが、なぜか母親もふくめ住民はふたりの不倫関係を確信。反論をいっさい認めない全体主義的な閉鎖社会のなかで集団の狂気が娘に襲いかかる。恐ろしい内容だが、娘はタフな精神の持ち主で、友人以上恋人未満の男とすったもんだ。いっぷう変わった恋愛沙汰にアイルランドの政治問題が濃い影を落とし、そこへさらにドタバタ喜劇をまじえた集団ヒステリーが発生、複雑な展開となっている。やや荒削りな構成でダイグレッションも多く、また長大なパラグラフに娘の内的独白や複数の会話、客観描写が連続するなど晦渋な文章だが、そこには人間性への深い洞察が読み取れる。まともな人ほど心に矛盾をかかえ、自身矛盾を感じない人ほど他人にレッテルを貼りたがり、その結果、正常な人間が異常者扱いされる異常な事態。事実を検証せず、自分の偏見と先入観に気づくこともなく、立場の異なる相手を糾弾する社会。現代の情報化社会への警鐘という点で本書のもつ意味は大きいが、娘が一連の事件を通じて成長する青春小説としても読めるところに救いがある。(9月6日)
3."Everything Under" Daisy Johnson (UK)[☆☆☆★★★] 冒頭は認知症の母親と同居する娘の話。とくれば、いわゆる「難病もの」か親子の断絶がテーマだろうと思ったが、以後の展開はそんな固定観念にもとづく予想をみごとに裏切るものだった。これは神なき現代における人間の運命を寓話的に描いた、『オイディプス王』の本歌取りともいうべき秀作である。が、その意図はすぐには見てとれない。16年前に失踪した母親を娘のグレーテルが探しまわる一方、その昔、テムズ川へとつづく運河で母とふたり、ボート暮らしをしていた時代を回想。また一方、当時ふたりの前に現れた少年の冒険物語もスタート。この三本立ての進行が巧みでサスペンスにあふれ、ハートウォーミングなふれあいと緊張の一瞬が交錯するなか、『オイディプス王』を思わせる複雑な人物関係が次第に明らかになる。むろんギリシア悲劇のように神とひととの劇的対立はありえず、そのぶんスケールの小さいドラマではあるが、それは現代文学の宿痾。にもかかわらず、グレーテルが辞書編纂者となった経緯からうかがえる「始めに言葉ありき」という言語、そして愛と血のつながりとしての家族、この両者が人間の思考と行動を決定づけるもの、すなわち運命であることを本書は如実に物語っている。神なき現代にあって運命のもつ具体的な意味にこれほど迫った試みもめずらしい。古典劇のような劇的感動こそ得られないものの、その試みを大いに評価したい。(8月9日)
4."In Our Mad And Furious City" Guy Gunaratne (UK) [☆☆☆★★★] ビートの効いたリズミカル、エネルギッシュな文体にまず惹かれた。実際ラップに夢中の少年も登場するなど、これはロンドンの移民街が主な舞台の二世代にわたる青春群像劇である。むろん恋や友情、さらには音楽、サッカーといった定番の話題もあるが、なんといってもタイトルどおり、彼らがいずれも「狂気と怒り」の渦に巻きこまれるところが焦点。ベルファストのIRAとプロテスタント系住民、ロンドンのカリブ系黒人と治安当局、イスラム系住民と移民排斥を求める白人グループ。どの衝突にも山場があり、とりわけ最後、畳みかけるようなカットバックで複数の視点から描いた流血の大惨事がすさまじい。まさしく怒りと怒り、狂気と狂気の激突である。その巻きぞえになるのが純粋な少年たちで、若かりしころの彼らの親もふくめ、若者特有の素朴な正義感と、暴走する政治的イデオロギーや宗教感情とが当初から対比されている。フランス革命やロシア革命など、近現代における理想主義の栄光と悲惨の歴史をふりかえれば、この対比に青年作家らしい甘さがあるのは一目瞭然だが、移民問題でゆれるイギリスの現状においては、若者こそ希望をもたなければなるまいと推察する。ゆえにこの鮮烈なデビュー作は、まさに今日のイギリスそのものといえる作品である。(8月12日)
5."Warlight" Michael Ondaatje (Canada) [☆☆☆★★] 青春時代にはいつも嵐が吹き荒れるものだが、その舞台が本書のように第二次大戦直後、まだ空襲の傷跡が生なましいロンドンとなると、さぞ激しい嵐が吹き荒れたことだろう。そんな青春の嵐の象徴として見ると、本書の「戦火」はややもの足りない。焦点がぼやけ気味だからだ。両親が旅だったあと、突然カゴのなかの生活から解き放たれた少年がいろいろな人物と出会い、夜の大冒険をはじめる前半は謎に満ちて痛快。またそれが回想談ということでノスタルジーにあふれ、詩的な情景描写に見るべきものがある。読了後に意味のわかる伏線の張りかたもみごと。スパイ小説を思わせるアクションシーンもいい。が後半、提示された謎の解決篇となったところで視点がぶれ、また内容的にもスパイ小説、ロマンス、人情話、家庭小説、そしてもちろん青春小説へと拡散。どの話もよく出来ていて心の琴線にふれるのだが、強烈なインパクトに欠ける。ネタは割れないが唯一意外な顛末にしても、嵐が去って青春をうしない、若気のいたりに気づいたことへの感傷が主体で新味はない。なにより焦点が定まっていない点に不満をおぼえるが、過ぎ去った青春への挽歌としては佳篇である。(8月2日)
6."From A Low And Quiet Sea" Donal Ryan (Ireland) [☆☆☆★★] 心に深い傷を負った人びとの人生行路、とりわけ出会いと別れ、対立と和解を描いた輪舞形式の長編。終幕ですべてのピースがかみ合うものの、それまで全体像はまったく見えてこない。各話とも場面の途中からはじまり、それがようやくひとつの絵柄となったところでつぎの話。その絵柄と絵柄がなかなか結びつかない。とはいえ、随所に突然不安と緊張の高まる山場があり、思わず引きこまれる。騒乱の絶えないシリアから医師が妻子を連れて決死の脱出。アイルランドの田舎町で青年の運転する老人ホームの送迎バスが突然故障。同じくアイルランドの街で中年男が愛人のボーイフレンドと対決。医師も青年も中年男も、彼らと深くかかわる人びともそれぞれ、なんらかのかたちで愛に傷ついている。その屈折した心理を反映したかのような静かな海辺のひとときが、たまらなく切ない。一方、傷心を隠した陽気で下品なジョークは最高。こうした一見つながりのないピースがみごとに組みあって終幕へとなだれこむ。構成の妙が光る佳編である。
7."Washington Black" Esi Edugyan (Canada) [☆☆☆★★] 結末を除けば、物語としてはかなりおもしろい。19世紀中葉、バルバドス島の農園から、黒人奴隷の少年ワシントンが農園主の弟クリストファーの製造した飛行船で脱出。過酷な奴隷制の現実と、冒険小説の痛快さが同居する快調な滑りだしである。やがて舞台はカナダ北極圏、ノヴァスコシアの街と海、ロンドン、アムステルダム、モロッコの砂漠へと目まぐるしく変化。そのかんワシントンは人種差別に耐え、画才を認められて海洋生物学者の仕事を手つだい、水族館の建設を企画する一方、美しい娘と恋仲になったり、逃亡奴隷を追う賞金稼ぎの男と死闘を繰りひろげたり、さまざまな経験を通じて次第にたくましく成長する。突然スリルに満ちた危険な瞬間が訪れ、うぶな少年の心をときめかす甘美なひとときが流れ、農園時代の胸ふたぐ思い出も去来するなど緩急自在、鮮やかな場面転換は心憎いばかりだが、反面、善玉悪玉の色わけが目だち、奴隷制の扱いに見受けられるように皮相な人道主義も鼻につく。またスムーズな展開を重視するあまり、クリストファーとそのいとこ、父親など主要人物の心理が説明不足。最後、他人の苦しみは理解しがたいもの、という当たり前の真実がとって付けたように示されるとは、いったいなんのための恋と冒険の物語だったのか、と疑わざるをえない。ゆえに真実を知ったワシントン同様、読後の「心は空白」、感動はさっぱり湧いてこない。英ハードカバー版の楽しい表紙が予感させる文芸エンタテインメントに徹したほうが正解だったような気がする。(12月14日)
8."The Long Take" Robin Robertson (UK) [☆☆☆★] 歴史にはつねに光と影がつきもので、けっして光だけ、影だけが存在するということはない。ところが本書は、第二次大戦における連合国の勝利と、戦後のアメリカの発展という輝かしい歴史の裏にある暗黒面のみに焦点を当てている。すべて影のイメージで統一した、ひとつの長大な散文詩とも読める工夫は大いに評価できるし、主な舞台がニューヨーク、ロス、シスコとあって、当時のフィルム・ノワールを実況中継ふうに紹介したレトロな雰囲気も蠱惑的。が、主人公の復員兵ウォーカーの脳裏に去来するのは終始、戦争の残酷さ、悲惨さであり、新聞記者になった彼がたえず目にするのは、貧困、犯罪、人心の荒廃である。つまり、ここで描かれる歴史の暗黒面とは型どおりのものにすぎない。ユダヤ人の虐殺を中止させる手段として戦争以外になにがあったのか、と問うたオーウェルの悲劇的人間観とは雲泥の差である。また都市の再開発のためビルが破壊される場面から戦場の記憶がよみがえり、対照的に戦前のカナダの美しい自然、別れた家族や恋人を思い出すという展開が多く、ウォーカーの傷心がしみじみと伝わってくるのはいいが、これも次第にパターンが鼻につく。なるほど心の影、歴史の影、都市の暗部を見つめるのは詩人の仕事かもしれないが、ウィリアム・ブレイクのように人間の善悪両面に踏みこまなければ偉大な詩は生まれないものである。(9月9日)
9."The Mars Room" Rachel Kushner (USA) [☆☆☆★] 看板に偽りあり。主な舞台はシスコのストリップ・クラブ〈マース・ルーム〉ではなく、ロス近郊の女子刑務所だからだ。実際、主人公ロミーのダンサー時代の話より、彼女の刑務所生活のリポートのほうがはるかにおもしろい。施設の実態はもとより、ムショ仲間との交流や看守との対決、さらには、ほかの受刑者の悲惨な体験など、どのエピソードもよく出来ている。娘時代からの回想をはさんで過去と現在を交錯させ、またロミー以外の視点も取りいれることで、貧困や犯罪、児童虐待、人種差別、性差別など、アメリカのかかえるさまざまな社会問題が浮かびあがってくる。とりわけ、裁判・司法制度の矛盾については鮮やかな筆さばきだ。がしかし、ソローを思わせる「森のなかの生活」篇や、ロミーに関心をよせる法務教官の独白など、話が飛びすぎて一貫性に欠ける憾みもある。くだんの教官の人生経路に代表されるように、読んでいるうちは惹かれるが、読後に心にのこるものが少ない、まずまずの水準作である。(8月16日)
10."Normal People" Sally Rooney (Ireland) [☆☆☆] 精神医学はさておき、ノーマルとアブノーマルを峻別する基準はなにか。人間のどんな領域にどんな規範があるのか。これは神なき現代においては、すこぶる興味ぶかい問題のはずだ。ところが、作者にそんな問題意識はまったくない。公序良俗ですらほとんど扱われず、ある人物がまともか否かを決めるのはすべて、家族や友人のあいだで暗黙のうちに成立しているコンセンサスのみ。その実態はあいまいな気分にすぎず、本書の若いカップル、コネルとマリアンヌはいつも他人の物差しに従ったり反発したり、小さなサークルのなかでゆれ動いている。アイルランドの田舎の高校からダブリンの大学まで、ふたりの恋愛のもつれと葛藤が読みどころ。苦悩を通じて成長することこそノーマルな人間の姿なのだと、あらためて思い知らされる。が一方、周囲の男や女たち、とりわけマリアンヌの家族がいかにも浅薄な俗物でステロタイプ。ゆえに彼らと対峙するふたりの正常さもまた型どおりといわざるをえない。水準程度の青春小説である。(8月27日)
11."The Water Cure" Sophie Mackintosh (UK) [☆☆☆] 豪雨や猛暑など異常気象が地球規模でつづく昨今、J・G・バラードなどの破滅テーマSFはもはや絵空ごととは思えなくなっている。本書第一部、三人の視点から少しずつ紹介されるのは、有毒ガスで覆われた本土から避難した一家が遠くの島で生活する近未来の終末世界。ミステリアスな状況で、叙述形式も奏功して興味を惹かれる。ところが第二部、男たちが島に漂着、大黒柱が不在で女だけとなった上の一家と対峙するくだりでトーンダウン。危機が高まるわけでも、波瀾万丈のサバイバル物語がはじまるわけでもない。第三部ともども終末世界というより、男性優位のディストピア的な社会にあって、女性が愛の試練を経ながら成長していく姿がメロドラマをまじえて描かれる。ディストピアの実態は曖昧模糊として恐怖をおぼえるものではなく、危険はむしろ人間自身の心のなかにあるという指摘も平凡。いっそ破滅テーマに徹したほうが、よほどおもしろかったのではないか。(8月6日)
"Snap" Belinda Bauer (UK) "Sabrina" Nick Drnaso (USA)