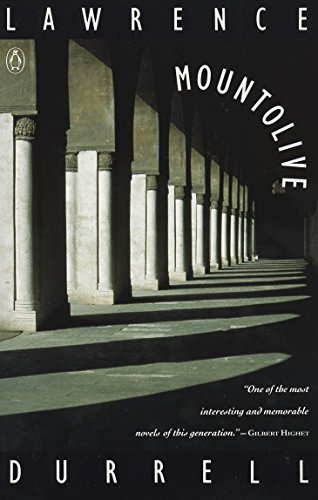Lawrence Durrell の "Mountolive"(1958)を読了。周知のとおり、"Justine"(1957)に始まる Alexandria Quartet の第三巻である。さっそくレビューを書いておこう。
[☆☆☆☆★★] 驚いた。じつにおもしろい。四部作の第三巻でありながら、これから読みはじめても、じゅうぶんに楽しめる大傑作である。成功の秘訣はまず、前巻まで端役にすぎなかった若き駐エジプト大使、マウントオリーヴを中心に据えたこと。これにより、同じ時代、同じ顔ぶれなのに人物関係が一新されたかのような印象を受ける。話法の変化がもたらした効果も大きい。前巻までは「私」の叙述に他人の手紙や日記などがまじる一人称多視点スタイル。それが本書では三人称で最初から複数の視点が導入された結果、より多くの場面で、より多くのエピソードが展開。それゆえ物語性という点で前二作をしのぐ抜群の仕上がりとなっている。そのぶん、「愛の探求」を通じて人間存在の本質に迫る試みは、形而上学的な抽象論としては影をひそめるが、一方、ひとはひとを純粋に愛しうるか、愛とはなんらかの打算をともなうものではないか、という古典的なテーマが政治陰謀劇、あるいは上質のメロドラマのなかで提示される。このため第一巻のジュスティーヌをめぐる四角関係、さらには第二巻の五角関係がまったく新しい意味をもち、恋愛とは別次元のものに変化。「異なる真実は相補的なものか、互いに否定しあうものか」という問いが、第二巻のみならず本巻もふくめ、作品全体について投げかけられていることがわかる。つまり本書は、ここまでのたんなる補完ないし異稿ではなく、一連の作品にコペルニクス的転回をもたらす役割を担っている。驚くべき神わざだ。当然、読者は前二作と本書の再読を余儀なくされ、いかなる結論が待ちうけているのかを知るべく最終巻を読まねばならない。こんな四部作の第三巻は空前絶後ではなかろうか。舞台は民族、宗教、言語によって相貌を変化させる街アレクサンドリア。時代は風雲急を告げる第二次大戦前夜。感服した。