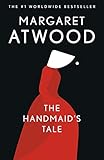前々回だったか、mathematical infallible happiness(p.2)という本書の一節を引用したが、同様のくだりはほかにもある。the great strength of logic purifies everything (p.22) there is nothing happier than digits, living according to the well-constructed, eternal laws of the multiplication table. Without wavering, without erring. The truth is one, and the true path is one.(p.59)
こうした幸福論にもとづく絶対無謬の世界がユートピアであり、かつディストピアでもあるのは、この思想が幸福を、地上の楽園を約束すると同時に、falliability, wavering, erring を全否定するらだ。そこには価値判断の自由も、行動選択の余地もいっさいない。言い古されたことの繰り返しになるが、Zamyatin はロシア革命直後からいち早く、彼の国の将来を憂えていたわけである。
一方、21世紀の東洋の島国にも、上のような全体主義に近い思考回路の人たちがいる。自分の考えがつねに、あるいは完全に正しく、自分とは異なる立場がつねに、あるいは完全に間違っている、と主張しているとしか思えない人たちだ。「……よ、お前は人間じゃない。たたっ斬ってやる」というようなアジテーションをぶち上げ、それに同調する人たちである。この人たちは敵対者をヒトラー呼ばわりすることもあるようだが、自分自身のほうがよほどヒトラーに近い発想の持ち主であることにはまったく気づいていない。その扇動に乗ると集団ヒステリーが発生する。
新型コロナウイルスの問題にしても、いまだ医療専門家でさえ不明の部分があり、意見の相違も見受けられるというのに、すこぶる断定的に相手を批判し、自分の判断ミスは棚に上げ、いっさいの責任が他人にあるかのように訴える人たちがいる。何ごとも完全無欠の解決策などありはしないのに、それがどこかにあるかのように不満を述べる人たちがいる。集団ヒステリーの前ぶれである。
むろん、こと生命にかかわる問題だけに、falliability, wavering, erring は極力少ないほうがいい。しかし残念ながら、それを完全になくすことは神ならぬ人間には至難の業、というのが冷静な判断だろう。それなのに万能薬、絶対無謬の方策を求める人はあとを絶たない。「人間からどんなものでも抹消することができようが、絶対への欲求だけは消すことはできまい」とE・M・シオランは述べた。この「絶対への欲求」が全体主義への誘惑でもあることは、上に引用した Zamyatin の言葉からも明らかだろう。
さて、これまで全体主義を観念型と集団ヒステリー型に分けて雑ぱくな私論を展開してきたが、この問題についてはとうてい語りつくせないので今回でおしまい。代わりに、"We" もふくめ、ぼくが英語で読んだことのあるディストピア小説のなかから、マイルストーン的な名作をいくつか挙げておこう。月並みなリストでお恥ずかしい次第だが、あえて奇をてらうこともあるまい、とあきらめた。なお、採点はどれもお遊びです。
1."Demons" Fyodor Dostoevsky(1871-72 ☆☆☆☆★★)
実際に読んだのは Penguin Classics の旧版。ディストピアそのものは登場しないが、その理論的基盤を知るうえで Dostoevsky は必読。ほかに推薦したい作品もあるが、英訳では未読なので割愛。
2."We" Yevgeny Zamyatin(1920 ☆☆☆★★★)
3."Brave New World" Aldous Huxley(1932 ☆☆☆☆★)
4."Nineteen Eighty-Four" George Orwell(1949 ☆☆☆☆★★)
3,4とも学生時代に読んだきりだが、新型コロナウイルスの感染源になった全体主義国を思い浮かべると、とりわけ Orwell の先見性には舌を巻くばかり。
5."The Handmaid's Tale" Margaret Atwood(1985 ☆☆☆☆)
物語として、とにかく面白かった憶えがあるが、いま読むと☆☆☆★★★くらいか。