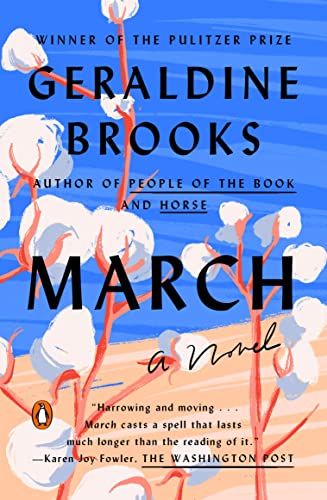仕事の目途はだいぶついたのだが、相変わらず多忙で本が読めない。またまた昔のレビューを引用することになってしまった。
[☆☆☆★★] 06年度のピューリッツァー賞受賞作。またもや南北戦争の話かと、大して期待もせずに読みはじめたが、手馴れたストーリーテリングに加えて着想の妙が光り、けっこう面白い作品だった。というのも、主人公は何と、『若草物語』の四姉妹の父親マーチ!同書では戦争に従軍、最後にちらっと顔を出すだけだったが、本書ではその従軍記録や黒人たちとの交流などが紹介され、後書きで作者も述べているように、父親を前面に押し出すことで『若草物語』の空白部分を埋める外伝となっている。戦地から帰還したマーチが四姉妹と再会する結末など、旧作と同じ場面ながら、過酷な戦争体験を経た人間の視点から描かれており、新旧両作の相違が一目瞭然。『若草物語』が心温まるホームドラマであるのに対し、本書は陰影に富んだシリアスな作品と言えるだろう。ここではマーチ夫妻は熱心な奴隷解放運動家であり、悲惨な奴隷の生活が描かれる一方、マーチの従軍と負傷を通じて、戦争がもたらす悲劇と、戦争に参加する個人の良心という問題も提出される。それは結局、正義のための戦争は是か非かという根本問題であるはずだが、作者はあくまでも情緒的な描写に終始。「シリアス」と言ってもその程度なのが評者には不満だが、作者のねらいはホームドラマの外伝なのだから、理屈ぬきに劇的な展開を楽しめばいいのかもしれない。英語は時代を反映した古風な表現が目立つが、決して難解というほどではない。 …決して出来の悪い作品ではなく、ぼくもご祝儀にたくさん星をつけたが、重大な問題に軽くふれるだけという現代作家特有の突っこみの甘さはいかんともしがたい。南北戦争に対するブルックスの立場は要するに、二つの「今日的な常識」に基づいている。一つは、奴隷制度は悪であるという見方であり、もう一つは、戦争は悪であるという判断だ。では、奴隷を解放するための戦争は是か非か? ブルックスはそういう倫理の問題を素通りし、ただもう情緒的に悲惨な奴隷の生活を描き、これまた情緒的に戦争の悲劇を訴えるだけなのだ。これでピューリッツァー賞受賞とは、現代文学の貧困を物語る一例と言ってもいいだろう。
一方、同じく戦争を題材にした作品で、ぼくが満点の評価を与えたのが Irène Némirovsky の "Suite Française " である。
…著者の死で未完に終わったのが本当に惜しまれる作品だ。完成していれば、『誰がために鐘は鳴る』や『カタロニア讃歌』などと並ぶ戦争文学の不朽の名作になっていたことだろう。イレーヌ・ネミロフスキーと上のブルックスとでは、もうまるで人間の捉え方が違う。ブルックスも人の悲哀や苦悩を描いているが、それは奴隷制と戦争に関する「大衆の常識」に安住した表面的な処理にしか過ぎない。その点、ネミロフスキーには、人間がどれほど美しく、同時にまた、いかに醜い存在であるかという痛切な認識がある。エゴイズムへの絶望と、その絶望の彼方にあるかすかな希望。希望がなければ絶望も生まれない。こうした人間の栄光と悲惨をめぐる葛藤は、ヘミングウェイやオーウェルの世界にも通じるものだ。
この駄文を書くにあたり、ネットで戦争文学について少し調べてみたら、某図書館が発表した「戦争文学ベスト30」というのが目についた。その中で『誰がために…』がベストワンに輝いているのはいいとして、また、この "Suite Francaise" が載っていないのも未訳ゆえに仕方がないとして、オーウェルの作品がすっかり忘れられていることにぼくは驚いてしまった。
オーウェル・ファンの間では有名な話だと思うが、彼は "Reflections on Gandhi" というエッセイの中で、ホロコーストを中止させるための戦争は是か非かという問題を提起している。アウシュヴィッツで獄死したユダヤ人作家、ネミロフスキーにとって、ホロコーストが文字どおり死活問題であったことは言うまでもない。彼女がそれにどう取り組むはずだったかは、遺された本書の断片から推測するしかないが、ぼくはぜひとも完成稿を読みたかった。
ともあれ、その某図書館の副館長も述べているように、戦争は「極限状態」である。この言葉を平和な時代に口にするのは簡単だが、では実際、人は極限状態に置かれたとき、何ができるのか。何をすべきなのか。どんな行動に走るのか。オーウェルとヘミングウェイ、そしてこのネミロフスキーの作品を続けて読むと、人間の本質を知る上でいい勉強になるだろう。